「おすすめの自動車保険は?」「どの会社が一番いいの?」──
初めて車を購入する方の多くが、こうした疑問を抱えています。
本記事では、自動車販売業界で日本一の業績を誇る現役の車屋社長が、
数多くのトラブル事例と現場経験をもとに、初心者でも**「後悔しない最適解」**を導き出せるよう、
保険選びの基礎から裏ワザまでを徹底解説します。
1. 絶対に「無制限」にすべき!基本の補償3つ
まず最初に押さえるべきは、対人・対物・人身傷害の3つです。
ここでケチると、後から取り返しのつかない事態に陥ることがあります。
| 補償項目 | 推奨設定 | 理由・解説 |
|---|---|---|
| 対人・対物 | 無制限 | 事故の相手方に対する賠償は無制限で設定。億単位の請求が発生するケースもあり、上限を設けるのは非常に危険。 |
| 人身傷害 | 無制限 | 自分や同乗者が一生動けなくなるような事故の場合、3,000万円・5,000万円では到底カバー不可能。必ず無制限で。 |
2. 初心者こそ絶対に入るべき「車両保険」
保険料を大きく左右するのが、車両保険の有無です。
たしかに保険料は倍近くになりますが、初めて車を買う人ほど、加入を強くおすすめします。
▶ 車両保険の種類とおすすめ設定
| 種類 | 内容 | 推奨度 |
|---|---|---|
| 車対車限定 | 他車との接触事故のみ補償 | ✕ |
| 一般条件 | 自損事故(電柱衝突など)でも補償 | ◎ |
▶ 車両保険を外すとこうなる(実例)
ローンで月3万円、保険料1万円の支払い。
「車両保険を外して節約しよう」と思い、加入しなかった場合──
もし全損事故になれば、車は廃車、でもローンは5年間支払い続けることに。
実際、こうしたケースを毎年のように見てきました。
そのリスクを考えると、車のグレードを下げても車両保険は外さないのが賢明です。
3. 保険料を安く抑える「免責設定」という裏技
「車両保険に入りたいけど高い…」という場合は、免責(めんせき)金額の設定を検討しましょう。
例)免責10万円に設定
→ 保険料が月2万円 → 約1.7~1.8万円に下がるケースも。
免責とは「事故の修理費100万円のうち、最初の10万円は自己負担」というルール。
多くのケースでは、相手側に過失があると免責が適用されないため、実質的なリスクは低めです。
初心者のうちは「免責あり+車両保険付き」で入るのが最もバランスの良い選択です。
💡特に18〜21歳は「保険会社が赤字」と言われるほど事故率が高いゾーン。
だからこそ、最初の数年は車両保険を必ず付けましょう。
4. 初心者は「代理店型保険」が安心
自動車保険には大きく分けて以下の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| ネット型 | 安い・手続きは自分で | 保険に慣れた人 |
| 代理店型 | 担当者が提案・手続き代行 | 初心者・忙しい人 |
保険料の安さだけでネット型を選ぶのは危険です。
特に初年度は、「代理店型」一択で間違いありません。
▶ 代理店型を選ぶ3つの理由
① 3年長期契約でトータル節約
3年間、等級が上がり続け、途中で事故を起こしても契約期間中は保険料が変わりません。
結果として、10万円以上の差になるケースもあります。
② 保険料が3年間据え置き
年々値上がりしている自動車保険ですが、長期契約なら料金が固定されます。
③ プロの提案で“無駄”が減る
代理店は運転者年齢・範囲・特約などを細かく調整してくれます。
結果的に、ネット型よりもトータルで安くなることも珍しくありません。
🔁 もし数年後に保険の仕組みが理解できたら、更新時にネット型との比較検討を。
5. 家族で節約!「等級シャッフル」で最大10万円安くなる
初めて車を買う18歳が自分名義で保険に入ると、6等級新規+年齢補正でかなり高額になります。
そこで活用できるのが「等級シャッフル」。
▶ 等級シャッフルの仕組み
- 父親(20等級)の保険を子供名義に移す
- 父親は新規6等級で再加入
これで、若者の高リスクゾーンでの保険料を家族全体で圧縮できます。
年間5万〜10万円の節約になることも。
✅ 家族名義で車を買う前に、「等級を譲れるか」必ず確認!
まとめ:車屋社長が推す“最適な保険の入り方”
| 項目 | 推奨設定・選び方 |
|---|---|
| 対人・対物・人身傷害 | 無制限 |
| 車両保険 | 一般条件+免責あり(例:10万円) |
| 保険タイプ | 初年度は代理店型で3年長期契約 |
| 特別テクニック | 家族間の等級シャッフル活用 |
🚗最後にひとこと
保険は「最悪のとき、自分と家族を守るための備え」です。
月々数千円をケチった結果、数百万円の負担を背負う人を、現場で何人も見てきました。
初めての保険こそ、慎重に、そして賢く選びましょう。

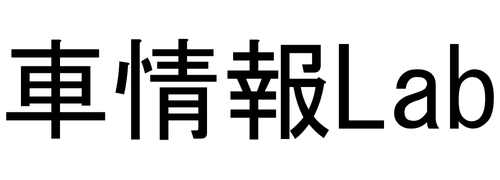
コメント